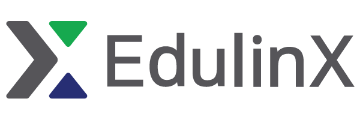明治大学 様
経験豊かな講師による実践的アドバイスが満載の「英語による授業を行うためのFD研修」


明治大学 様
明治大学国際連携本部様では、外国人留学生受入の推進や、英語学位コースの拡充等、大学の国際化推進に向けた取組事業の一環として「英語による授業を行うためのFD研修」を実施しておられます。
「英語による授業を行うためのFD研修」推進の背景と歴史
花野井 様
2009年から2015年頃までは、本学の教員がアメリカに渡航し、現地の大学で開催される英語授業のワークショップに参加していました。一方で、「日本国内で研修を実施してほしい」という声が多く寄せられていたことを受け、2016年からはアメリカの大学の教員を日本に招き、明治大学のキャンパス内で研修を行う形式に変更しました。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年度以降はオンラインでの実施に切り替えております。
補助金期間中の研修の特徴として、明治大学のニーズに合わせて「テーラーメイド」でプログラムが組まれていた点が挙げられます。依頼先には、明治大学専用のプログラムを構築・提供していただいていました。2024年度以降は、各社がお持ちのプログラムをそのまま採用できるようになり、今回EdulinX様のプログラムを導入させていただいた次第です。
EdulinXを選んだ理由
徳田 様
これまでのFD研修における大きな課題は、参加人数の少なさでした。本学としては、より多くの教員に参加してもらいたいと考えており、そのような中、EdulinX様から素晴らしい提案をいただきました。2024年度に実施した貴社のプログラム(基礎編及び実践編)には、それぞれ定員を超える申し込みがあり、多くの教員に関心を持ってもらえたことを嬉しく思います。これは、貴社のプログラムが以下の点で本学のニーズに合致した結果であると考えています。
- 半日から1日程度の短期間で実施できる。
- オンライン形式なので、本学の4つのキャンパスにいる教員が気軽に参加できる。
- 幅広い分野の教員に対応可能で、経験豊富な講師が担当してくださる。
横川 先生
先生方が参加しやすい環境を作ることが、本取組をスケールさせるために重要です。その意味で、貴社のプログラムは大きな魅力がありました。
担当職員からもありましたように、これまでは本学のニーズに特化したカスタマイズされたプログラムが必須でしたが、その場合、プログラム提供元に詳細な依頼を行い、関係者間で検討を重ねるプロセスが必要となり、実施までに多くの工数がかかりました。これで参加者数が50名や100名規模にスケールするのであれば、こうした手間を掛ける必要性を感じるものの、参加者数はその数には及んでいませんでした。
そのため、既に多くの大学で実績のある貴社のプログラムでそのまま依頼できることは、人的リソースの有効活用の観点から、ありがたいと感じました。また、吉中講師のことは個人的に存じ上げており、その実績にも信頼があるため、安心してお願いできると感じました。
そして、使用言語が日本語である点も、本学にとっては大きな決め手でした。これまではEMI(English Medium Instruction)を受講生として体験していただくために、英語を母語とする大学教員にFD研修講師を依頼していました。このこと自体は非常に意義があると思いますが、参加者の英語習熟度にばらつきがあり、研修に対する理解度やコミットメントに差が出てしまうことがありました。
「英語で授業を行うための研修なのだから、英語で行うのが当然でしょ?」という考え方も勿論ありますが、ほとんどの参加者の母語が日本語なのであれば、日本語で研修を行っていただくほうがより効果的だと考えました。
研修に対するご感想
花野井 様
吉中講師は、非常におだやかな雰囲気と語り口でありながら、その内容は豊富な経験に基づき、説得力がありました。
受講者の感想としては、「基礎編」に参加した先生からは、「シンプルな英語表現で授業をすればよいと学べた」「授業でよく使える英語フレーズを学べて有益だった」「英語での自己紹介で度胸がついた」といったものがあり、多くの先生が英語で授業をすることへの不安を払拭されたようです。
「実践編」参加者からは、「アイスブレイクで相互理解が深める手法が良い気づきとなった」「対応に苦慮する学生に対する対処の具体例が非常に参考になった」と、高い満足度が伺える感想が寄せられました。
徳田 様
「基礎編」と「実践編」に共通して多かった感想は、次の通りです。
「半日の研修は長く感じるかと思ったが、講義とグループワークのバランスが良く、夢中になっているうちに終わった」「グループワークが有益だった」「吉中講師の講義は、普段の日本語での講義にも役立つ内容だった」といったものでした。
2024年度は4回のFD研修を実施しており、そのうち1回が英語母語話者である講師によるFD研修でしたが、英語での双方向型研修に戸惑う参加者も見られました。参加者によって英語での研修への慣れや経験が異なる中、吉中講師の日本語での研修は、多くの方にとって安心して参加しやすいものだったように思います。
横川 先生
私は、アメリカの大学からお招きした先生によるFD研修に参加した経験があり、国内にある海外大学の先生によるFD研修のコーディネーター役を務めたこともあります。そして今回、吉中講師の研修を聴講し、特長として気づいた点があります。
まず、今回はオンラインでのFD研修でしたので、対面型の研修とは異なる制約がある中、吉中講師は受講生とのラポール(信頼関係)をしっかりと築き、心理的安全性を保つ研修の場を素早く作り上げておられました。その力量に深く感銘を受けました。
そして、英語母語話者によるFD研修では、授業の組み立て方や、要素、ストラテジーなど、大きなフレームワークについては紹介されますが、総じてそれらを実践するための具体策や英語での表現方法については、参加者の判断に委ねられているという印象があります。一方で、非英語母語話者の教員にとっては、例えば「どのタイミングでどのように語り掛けるか」といったような、個別具体な情報も非常に重要だと考えています。
吉中講師の研修では、英語表現や授業で有効なWPM(Words Per Minute)やシラブル数など、具体的な例が多く提示されていました。英語による授業に関して幅広い習熟度の先生方に向けて、具体例を紹介することは非常に難しい事ではないかと思いますが、そこを踏み込んで提供してくださいました。これは勇気のいることだと思いますが、吉中講師はそれを敢えて行ってくださり、とてもありがたいことだと感じました。
これからの展望・課題
花野井 様
過去の研修でも、EMIの経験や英語力に差がある先生方が一緒に受けることがよくありました。今回の研修でも、「基礎編」と「実践編」に分けて実施しましたが、参加者のレベル差について言及された方もいらっしゃいました。今後は、参加者のレベルをどう線引きするかが課題だと感じています。
徳田 様
今回参加された先生方の約3割は、これまでにも本学のFD研修に参加したことのある方でした。2025年度に向けては、リピーターと新規参加者それぞれのニーズに合った研修内容をどう設計するかが課題だと考えています。
横川 先生
2024年度は、より多くの先生に参加してもらうために敢えて「基礎編」や「実践編」のような汎用性の高いタイトルを設定し、間口を広げたいという思いがありました。2025年度は、各回のターゲットオーディエンス、研修内容、タイトル付けを改めて検討していく必要があります。また、研修スケジュールの年間案内を年度はじめに示すことで、先生方がご自身のニーズやご都合に合わせて参加回を選びやすくなると思います。情報発信の方法についてもまだまだ工夫の余地があると認識しています。
花野井 様
横川先生がお話されたようなターゲットを明確化した運営計画も立てられる状況になりました。今回、経験豊富な講師がいらっしゃるEdulinX様にお願いできてとても良かったと思っています。
国際連携機構 特任教授
横川 綾子 先生

国際連携事務室
徳田 美保子 様

国際連携事務室
花野井 良典 様

CONTACT
学生から社会人まで、英語学習に留まらない
グローバル人材育成をEdulinXにお任せください。
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから